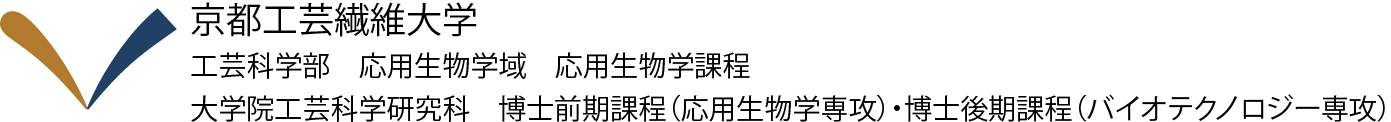ヒト遺伝病(乳児肝機能障害)の責任遺伝子の同定:国立生育医療研究センター他の医学部との共同研究(モデル生物を用いて検証に貢献しました)(バイオメディカルセンター)
バイオメディカルセンターと国立生育医療研究センター(要匡ゲノム医療研究部長), 東北大学医学部他の臨床研究機関との共同研究により、乳児肝機能障害の患者(非血縁の2症例)ゲノムに共通に見られたRint1(Rad50-interacting protein 1)遺伝子変異がその発症原因であることが明らかにされました。成果はJournal of Human Genetics (Springer Nature)に掲載されました。発熱を契機とした反復性の著明な肝障害(アミノトランスフェラーゼ上昇、凝固障害および高アンモニア血症を伴う)を示す2症例の全エクソームシークエンスを行った結果、どちらもRint1遺伝子のミスセンス変異あるいはスプライス部位の変異が両対立遺伝子に見られました。ヒトRINT1タンパク質は小胞と標的膜との融合に必要なSNARE複合体と相互作用し、膜輸送と脂質代謝において中心的な役割を果たします。変異体のRINT1組換えタンパク質は、小胞と標的膜との融合に必要なSNARE相互作用の異常を示しました。小胞体―ゴルジ体間の細胞内輸送が阻害されると小胞体ストレス経路が活性化されます(本HPトピックスアーカイブKatsube et al., 2019. doi: 10.1242/bio.046524)。患者細胞では小胞体ストレス反応(UPR)の標的遺伝子が発現誘導されていました。さらにオートファジーの障害も明らかになりました。以上の状況証拠から、患者細胞ではRINT1機能の喪失がUPRを活性化し、オートファジーを阻害すると言えます。これが原因となって肝臓で脂質貯蔵が異常になり、肝疾患の病態が現れるという可能性が示唆されますが、以上の状況証拠だけではRINT1がこの肝機能障害の責任遺伝子であると結論するには不十分でした。個体レベルでの検証が必要でした。そこで、ショウジョウバエをモデル系にして、Rint1の機能阻害が肝臓機能の低下をまねくか検討しました。その結果、ショウジョウバエのRint1をノックダウンすると、幼虫の脂肪体(哺乳類の肝臓と脂肪組織に相当)のサイズが正常と比べて有意に小さく、脂肪細胞の成長が抑制されていることがわかりました。また。細胞内に蓄積される脂肪滴の減少も確認されました。以上の結果から、上記の仮説すなわちRINT1がこの肝機能障害の責任遺伝子である可能性が強く示唆されました。