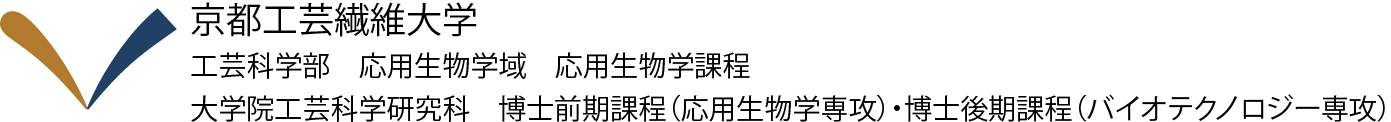精子を作る過程では減数分裂前にミトコンドリアの形態がダイナミックに変化することを超解像度顕微鏡、電子顕微鏡観察で明らかにしました(バイオメディカルセンター)
バイオメディカルセンターの松尾樹さん(応用生物学専攻修了)、井上喜博博士らは、ショウジョウバエの精子形成過程において、ミトコンドリアが顆粒状の形態から、複数が連なった『ミトコンドリアネットワーク構造』まで変化すること、後者の構造が減数分裂の開始に必要なことを明らかにしました。これらの成果を分子生物学の国際誌International Journal of Molecular Sciences (IF=4.9)に発表しました。
ショウジョウバエの精子形成過程では、減数第2分裂終了後に細胞あたり2個の巨大ミトコンドリアが作られ、最終的に1個の凝集体に集約されます。一方、減数分裂期あるいはそれ以前のステージではミトコンドリアがどのような形態をとるのかは明らかではありませんでした。本論文では高性能共焦点レーザー顕微鏡、超解像度顕微鏡、透過型電子顕微鏡を用いて、発生に伴い、ミトコンドリアが顆粒状(カプセル状)から複数が連なった『ミトコンドリアネットワーク構造』まで形態が変化してゆくことをつきとめました。この変化にはミトコンドリアの融合因子であるMarf、Opa1をはじめ5つの遺伝子が必要でした。精子形成過程では、減数分裂の前に細胞のサイズが大きくなる成長ステージが存在しますが、そこではATPの合成活性が高い、ネットワーク構造が形成されます。また減数分裂直前にもこのネットワーク構造が作られ、ミトコンドリアは分裂中でもATP合成を継続しながら、娘細胞に分配されることがわかりました。この機構は有糸分裂とは全く異なります。その時期にミトコンドリアの融合を阻害すると、減数分裂開始の引き金となるCdk1キナーゼが活性化されないことがわかりました。以上の結果から、エネルギーを必要とする動的な細胞現象である「減数分裂」を開始するには、ATP生産を効率的に行うことができるミトコンドリアが必要であり、その準備が整うまでは減数分裂を開始させない『チェックポイント機構』が存在するという説を提唱しました。ヒトをはじめ脊椎動物の精子形成過程でも減数分裂時に同じような制御系が働いている可能性があります。